タイムリーな引き寄せ著書に出逢う
「人格主義の回復」スティーブン・R・コヴィーより
療養期間中は読書に最適と、片端から再読やネットで取り寄せして読み漁っている日々。そんな中で先日からの気づきの命題にピッタリの内容を上記の著書から見つけ小躍り。これはブログにも紹介したいと続編としてお伝えすることにしました。
“刺激と反応の間”と題する項に書かれた、ヴィクトール・フランクル(訳注:オーストリアの精神科医・心理学者)という人物の衝撃的な体験の紹介です。
 以下上記著書より引用
以下上記著書より引用
心理学者のフランクルは、フロイト学派の伝統を受け継ぐ決定論者だった。平たく言えば、幼児期の体験が人格を形成し、その後の人生をほぼ決定付けるという学説である。人生の限界も範囲も決まっているから、それに対して個人が自らできることはほとんどない、というものだ。
フランクルはまた精神科医でもありユダヤ人でもあった。第二次世界大戦時にナチスドイツの強制収容所に送られ、筆舌に尽くし難い体験をした。
彼の両親、兄、妻は収容所で病死し、あるいはガス室に送られた。妹以外の家族全員がなくなった。フランクル自身も拷問され、数知れない屈辱を受けて。自分もガス室に送られるのか、それともガス室送りとなった人々の遺体を焼却炉に運び、灰を掃き出す運のよい役割に回るのか、それさえもわからない日々の連続だった。
ある日のこと、フランクルは裸にされ、小さな独房に入れられた。ここで彼は、ナチスの兵士たちも決して奪うことのできない自由、のちに「人間の最後の自由」と自ら名付ける自由を発見する。たしかに収容所の看守たちはフランクルが身を置く環境を支配し、彼の身体をどうにでもできた。しかしフランクル自身は、どのような目にあっても、自分の状況を観察者として見ることができたのだ。彼のアイデンティティは少しも傷ついていなかった。
何が起ころうとも、それが自分に与える影響を自分自身の中で選択することができたのだ。自分の身のおこること、すなわち受ける刺激と、それに対する反応の間には、反応を選択する自由もしくは能力があった。
収容所の中で、フランクルは他の状況を思い描いていた。例えば、収容所から解放された大学で講義している場面だ。拷問を受けている最中に学んだ教訓を学生たちに話している自分の姿を想像した。
知性、感情、道徳観、記憶と想像力を生かすことで、彼は小さな自由の芽を伸ばしていき、それはやがて、ナチスの看守たちが持っていた自由よりも大きな自由に成長する。看守たちには行動の自由があったし、自由に選べる選択肢もはるかに多かった。しかしフランクルが持つに至った自由は彼らの自由よりも大きかったのだ。それは内面にある能力、すなわち反応を選択する自由である。彼は他の収容者たちに希望を与えた。看守の中にさえ、彼に感化された者もいた。彼がいたから、人々は苦難の中で生きる意味を見出し、収容所という過酷な環境にあっても尊厳を保つことができたのである。
想像を絶する過酷な状況の中で、フランクルは人間だけが授かった自覚という能力を働かせ、人間の本質を支える基本的な原則を発見した。それは刺激と反応の間には選択の自由がある、という原則である。中略
私たち人間が動物のように本能や条件付け、置かれた状況だけに反応して生きていたら、無限の可能性は眠ったままである。以上引用終わり
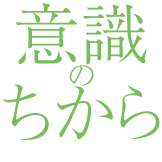

コメントはこちらから