今、なぜアーレント?(3)
第2回は、国民国家を解体へと向かわせ、やがて全体主義にも継承されていく「人種主義」「民族的ナショナリズム」という二つの潮流がどのように生まれた かを明らかにしていくという内容。
アーレントは、全体主義を形作った要素のひとつとして帝国主義を重視しているが、第一巻では国民国家の中で、ユダヤ人が内部の異分子、敵として浮上し、その意識が帝国主義の争いの中で、人種主義と呼ばれるような思想に転換していった、これが拡大していったことで、実は国民国家自体の根幹が揺らぎ始める。
まず、帝国主義がどのように人種主義思想生んでいったのか・・
19世紀末、イギリスやフランスなどの帝国主義が標的としたのがアフリカ大陸だった。中でも、アジアに向かう中継地に過ぎなかった南アフリカは、1870年代以降、ダイヤモンドや金の鉱山が発見され、ヨーロッパから大量の人がなだれ込んでくる。国家を共有する人たちから成り立っている国民国家はそこで、今まで見ることのなかった西洋文明とは異なる暮らしをする人々と出会う。
ヨーロッパ人の目には、みかけも風習も異なる彼らは、理解不能な存在として映った。彼らに国民国家の一員として人権や法の保護を与えることはできなかった。そこに19世紀末の帝国主義の大きな矛盾があった。
なぜ支配されなければならないのか、植民地の人々の間に自然に起こる自治の意識に対抗するためには、新たな政治的支配装置が必要だった。それが人間には人種というものがあって、そこには優劣があるという人種思想だったのだ。フランスの小説家・アルテコール・ド・ゴビノーは、白人が生物学的に優れているという人種理論を提唱した。白人は、植民地の人々に、神のようにあがめられる存在なのだと考える根拠を与えた。
アーレントは、第二巻の中で、イギリス人作家のジョセフ・コンラッド著「闇の奥」(1899年)をかなり引用しているが、この中でイギリス人クルツがアフリカの奥地で神のようにあがめられる存在になるという話になっている。ちなみに、クルツというのは、フランシス・コッポラ監督の「地獄の黙示録」(ベトナム戦争中 米軍のカーツ大佐が密林に王国を築く)の中のカーツ大佐のモデルとなっている。 キリスト教的な神学がちょっと歪んでるよう、自分たちはこういう野蛮なものを支配する、世界を治める支配を神から与えられているといったような。自たちが導いてやらないと彼らもどうしようもない、彼らのためにもなる、そういうことがこの人種思想としてヨーロッパ大陸にもどっていく。「国民国家」の構成員たちが、自分のアイデンティティー強化するためのツールになってしまったというメカニズムが働いているのではないか。
舞台をドイツに戻すと・・その人種思想がドイツにおいて、どのように変化していったのか。 ドイツにおける帝国主義は、イギリスやフランスなど他の西欧諸国とは別の道を辿った。1871年に国家統一したドイツは、イギリス人が行ったようなアジア、アフリカへの植民地進出に出遅れる。そのため、ヨーロッパ大陸内で支配地域を広めることを目指すようになる。これを大陸帝国主義という。ドイツ帝国は、1890年以降、東ヨーロッパやバルカン半島進出の野心を抱き、これが第一次世界大戦の原因のひとつとなる。しかし、ドイツ帝国は敗戦。新たに誕生した1919年、ワイマール共和国がドイツ人の民族意識を高揚させるドイツの歌を国歌に制定する。敗戦の痛手の中、歴史的にドイツ民族が住んでいた守るべき土地の広大さに想いを馳せたのだ。
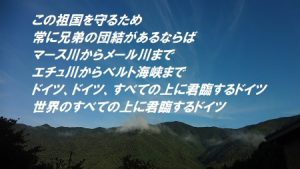 この歌にはヨーロッパ国家大陸に広がる民族の地に対する誇りが象徴されていた。やがてドイツは、大昔からドイツ民族のものであるはずの領土を取り戻さなければいけないと考える。それがナチスが解明した民族的ナショナリズム、「土地の共同体」として民族の統一を目指すものだった。しかし、ドイツが求めた広大な領域は、実際にはドイツ人以外の民族が多く住んでいた。アーレントは書いている。 ドイツ民族こそが最上位の民族である、他のヨーロッパの民族を支配する権利があると考えたのだ。ドイツ民族の居住地域は、こういう狭い所じゃなくて、もっと東に広がっているんじゃないか、大戦で失った所だけじゃなくて全部自分たちのものにすべきだという発想。ドイツでナチズムが台頭したら危ないって話をするときに、またこの歌が聴こえてきそうだとよく引き合いに出される歌。
この歌にはヨーロッパ国家大陸に広がる民族の地に対する誇りが象徴されていた。やがてドイツは、大昔からドイツ民族のものであるはずの領土を取り戻さなければいけないと考える。それがナチスが解明した民族的ナショナリズム、「土地の共同体」として民族の統一を目指すものだった。しかし、ドイツが求めた広大な領域は、実際にはドイツ人以外の民族が多く住んでいた。アーレントは書いている。 ドイツ民族こそが最上位の民族である、他のヨーロッパの民族を支配する権利があると考えたのだ。ドイツ民族の居住地域は、こういう狭い所じゃなくて、もっと東に広がっているんじゃないか、大戦で失った所だけじゃなくて全部自分たちのものにすべきだという発想。ドイツでナチズムが台頭したら危ないって話をするときに、またこの歌が聴こえてきそうだとよく引き合いに出される歌。
 19世紀に入って、ナショナリズムがだんだん高まっていく中で、「国民」Nationでは、概念が狭いんじゃないか、「国民」は、自分たちが一つの政治的単位であるべだ、自分たちで自治をすべきだと明確な意識を持った人たちの集まり。そこで、「民族」Volk(フォルク)という概念が意味を持ってくる。英語のフォークダンスのフォークだとか、もともとは民族という単純な意味だが、自分たちの先祖が生きていた所というのは、自分たちの同胞がまだいて、もっと広大に広がっているんじゃないか、先祖が住んでいた土地も「民族」Volkとして一体なのだ、という意識が生まれてきた。それが民族ナショナリズムの始まり。最初はもっと素朴に、先祖が住んでた土地を訪問しようという運動が・・
19世紀に入って、ナショナリズムがだんだん高まっていく中で、「国民」Nationでは、概念が狭いんじゃないか、「国民」は、自分たちが一つの政治的単位であるべだ、自分たちで自治をすべきだと明確な意識を持った人たちの集まり。そこで、「民族」Volk(フォルク)という概念が意味を持ってくる。英語のフォークダンスのフォークだとか、もともとは民族という単純な意味だが、自分たちの先祖が生きていた所というのは、自分たちの同胞がまだいて、もっと広大に広がっているんじゃないか、先祖が住んでいた土地も「民族」Volkとして一体なのだ、という意識が生まれてきた。それが民族ナショナリズムの始まり。最初はもっと素朴に、先祖が住んでた土地を訪問しようという運動が・・
 ワンダーフォーゲルからナチスまで、どこがおかしい? 経済的な意味での閉塞感と政治的な要因が絡んでいる。自分たちが発展する土地を確保しなければならない、東しかない、勢力圏だとしたときに、民族的なつながりがあるから、それを正当化材料として使いたいという欲求が出る。それが、第一次世界大戦の敗戦でドイツは領土の13%を失う。しかも、賠償金も。いよいよ手詰まり。そうすると、関連的に自分たちのものだったのにという喪失感がよけい強くなってくる。さらに、アーレントは、帝国主義の時代に生まれたもう一つの問題について書いている。
ワンダーフォーゲルからナチスまで、どこがおかしい? 経済的な意味での閉塞感と政治的な要因が絡んでいる。自分たちが発展する土地を確保しなければならない、東しかない、勢力圏だとしたときに、民族的なつながりがあるから、それを正当化材料として使いたいという欲求が出る。それが、第一次世界大戦の敗戦でドイツは領土の13%を失う。しかも、賠償金も。いよいよ手詰まり。そうすると、関連的に自分たちのものだったのにという喪失感がよけい強くなってくる。さらに、アーレントは、帝国主義の時代に生まれたもう一つの問題について書いている。
1914年に始まった第一次世界大戦、帝国主義同士が激しくぶつかり合ったこの戦いは、各地に多くの難民を生み出した。ヨーロッパの国々は、次々と自国にいた多民族を領土から追放、国家の正員としての身分を奪って、多くの無国籍者を生み出したのだ。
 アーレントは、無国籍者こそ、戦争の最も悲惨な産物であると訴えた。どの国家も受け入 れられないほどに発生した難民は、どこからも法の保護を受けられない存在となったのだ。アーレントは、無国籍者の問題とは、彼らが法によって守られていないというだけでなく、人間が生まれながらに持っているはずの権利まで失ってしまったことにあると考える。それは、フランス革命以降、人々が信じてきたヨーロッパの人権の概念(1789年人間と市民の権利の宣言)を覆すものだった。こうして、普遍的な人間性は失われ、国民国家の内部でも、ユダヤ人全ての人権を奪うという全体主義へ時代は加速していく。
アーレントは、無国籍者こそ、戦争の最も悲惨な産物であると訴えた。どの国家も受け入 れられないほどに発生した難民は、どこからも法の保護を受けられない存在となったのだ。アーレントは、無国籍者の問題とは、彼らが法によって守られていないというだけでなく、人間が生まれながらに持っているはずの権利まで失ってしまったことにあると考える。それは、フランス革命以降、人々が信じてきたヨーロッパの人権の概念(1789年人間と市民の権利の宣言)を覆すものだった。こうして、普遍的な人間性は失われ、国民国家の内部でも、ユダヤ人全ての人権を奪うという全体主義へ時代は加速していく。
 スタジオでの解説・・ 建前を言えば、普遍的人権がある以上は、どこか近くにある国が引き受けるべきだが、実際には国家というのは、NationをベースにしてNationの利益を守ろうとしてきたわけなので、自分のNationに属していない人間まで守ってやる義理はない、そういうことが第一次世界大戦で露骨に明らかになってしまった。
スタジオでの解説・・ 建前を言えば、普遍的人権がある以上は、どこか近くにある国が引き受けるべきだが、実際には国家というのは、NationをベースにしてNationの利益を守ろうとしてきたわけなので、自分のNationに属していない人間まで守ってやる義理はない、そういうことが第一次世界大戦で露骨に明らかになってしまった。
キーワードは「同一性」。自分たちの同一性を強めることによって、国家としての一体性というのを保ってきた。功罪両面あって、例えば、教育水準を上げようとしたら、国語を統一しないといけない、他に、軍隊とか警察とか命を懸けて戦う人たちにとっては自分たちが守るべきもののイメージがちゃんとないといけない、国家をちゃんと強化して、人々を幸福にしていく、安全保障を確保していく上で、大事だったが、それに頼りすぎたせいで、同一性というのが予想を超えて、だんだん人々に求められるようになっていった。それが結局のところ、ヨーロッパ文明が築き上げた普遍的人間性の理想の限界、そういうのが見えてきた。アーレントはそれがショックだったのだろう。
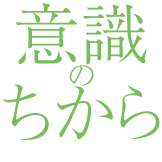

コメントはこちらから